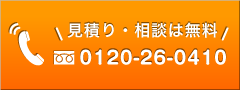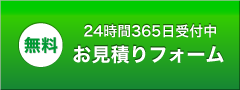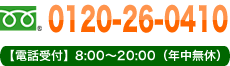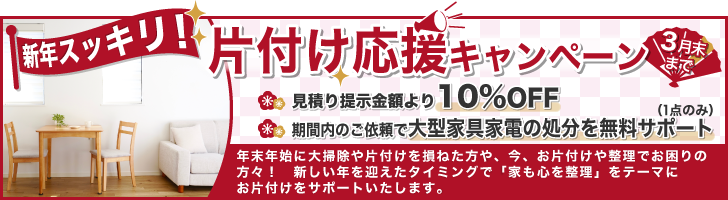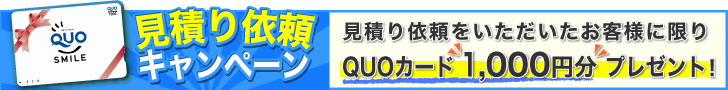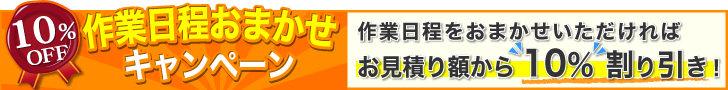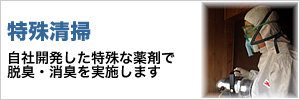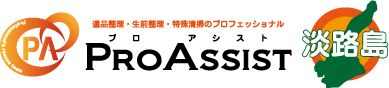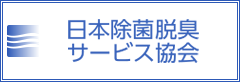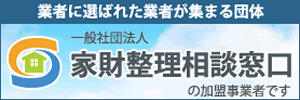大切な人がなくなると、悲しみに暮れる間もなく、葬儀や様々な手続きをしなくてはなりません。
同時に、相続が発生し申告期限内に相続税の申告をする必要があります。
そして忘れてはいけないのが、遺品整理です。

きちんと整理し、送ってあげることも、個人へのご供養のひとつになると思います。
遺品整理をいつ始めるべきなのか、タイミング(時期)や注意点などを紹介したいと思います。
ー 目次 ー
*タイミング(時期)の目安
*遺産相続とは?
*賃貸から撤去するときの注意点
*まとめ
・タイミング(時期)の目安
親族が納得のいくタイミング(時期)で遺品整理を行い故人への気持ちの区切りをつけることが大切ですが、各家庭の諸事情や自己所有物件か賃貸物件なのか、期日制限の有・無によっても変わってきます。

※亡くなってすぐ・葬儀終了後
遺族が遠方に暮らしているなど、何度も足を運んだりなかなか時間が取れない場合など、葬儀の直後に遺族でそろって整理するのも、ひとつの手です。
※諸手続き終了後
家族や親族が亡くなると、多くの手続きをしなければなりません。すべて終わらせるだけでも、相当な労力が必要となります。
こうした大変な手続きが、すべて終了し少し落ち着いてから、遺品整理をする方も多くいます。
※賃貸物件の場合
賃貸物件などの場合、決められた契約上のルールがあり、家賃や部屋の退去の関係で、月末や翌月末など、家賃が発生しないタイミングで、遺品整理をして退去することを、おすすめします。
※四十九日の法要後
遺品整理のタイミングで最も多いのは、四十九日の法要後です。気持ちも少し落ち着き、親族が集まる機会でもあるため形見分けなどもやりやすくなります。
※相続税が発生する前
相続が発生してから、10ヶ月以内に申告・納税をしなければなりません。その時期を目安にして、遺品整理をする方もたくさんいます。
※持ち家(自己所有物件)の場合
住まいに期日の制限がない場合、気持ちの整理がついてから、自分のペースでゆっくり遺品整理を進めるといいでしょう。
・遺産相続とは?

遺産相続とは、亡くなった人の財産を残された家族が引き継いで分配する一連の手続きのことです。
相続が起きる前のものは「財産」といいますが、相続が起きた途端に「遺産」にいい方が変わります。
個人が持っている貯金等の現金や、土地・建物・証券などをプラスの財産といい、形がない権利(著作権・債権・借地·借家権など)や借入金・債務なども含むすべてが遺産相続の対象になります。
相続開始から、相続をするかしないか(相続放棄・限定承認)を決定する期間は3ヶ月、相続税の申告期限は10ヶ月となります。相続の手続きにはわからないことや難しいことがたくさんあると思います、そんな時は、弁護士会や税理士会の無料相談や市区町村役場の無料法律相談などを利用されるといいでしょう。
・賃貸から撤去する時の注意点

賃貸物件などにお住まいだった故人のお部屋を片付ける際には、決められた契約上のルールがあります。
設置したエアコンや家具などの撤去、水回りを含め簡単なハウスクリーニングしなければならないなど、原状回復が求められます。翌月になってしまうと家賃が発生してしまいます。家賃の支払い、契約期間や退去日など賃貸契約書を確認し、余分な出費をおさえるためにも、賃貸の場合は、できる限り早い時期に遺品整理をする必要があります。
・まとめ

思い出が詰まった遺品などは、整理しにくいものですが、いつかは片付けなければなりません。
遺品整理だけではなく、故人が亡くなったあとに残る手続きなども、大変労力が必要となります。少しでも負担を軽減するために専門業者に依頼するのも選択肢の一つです。
遺品整理は悲しみを乗り越えるための第一歩です。
故人の残したものを一つひとつ丁寧に整理していくことで悲しみも徐々に落ち着いていくでしょう。
始めるタイミング(時期)や整理の方法は人それぞれです。無理に整理を開始するのではなく、気持ちや状況が落ち着き自分にとって適切なタイミング(時期)を見極めて取り掛かるといいでしょう。
新着情報
- 2025/2/9

【作業実績】
茨木市の賃貸物件にてご遺品整理を実施しました。... - 2025/1/29

【スタッフブログ】
どこから手を付けたらいいかわからない…女性専任スタッフが一緒... - 2025/1/27

【作業実績】
居間のお片付けで広がる安心感ー吹田市にお住まいの高齢女性のお... - 2025/1/22

【作業実績】
洲本市の賃貸物件で生前整理を実施しました...